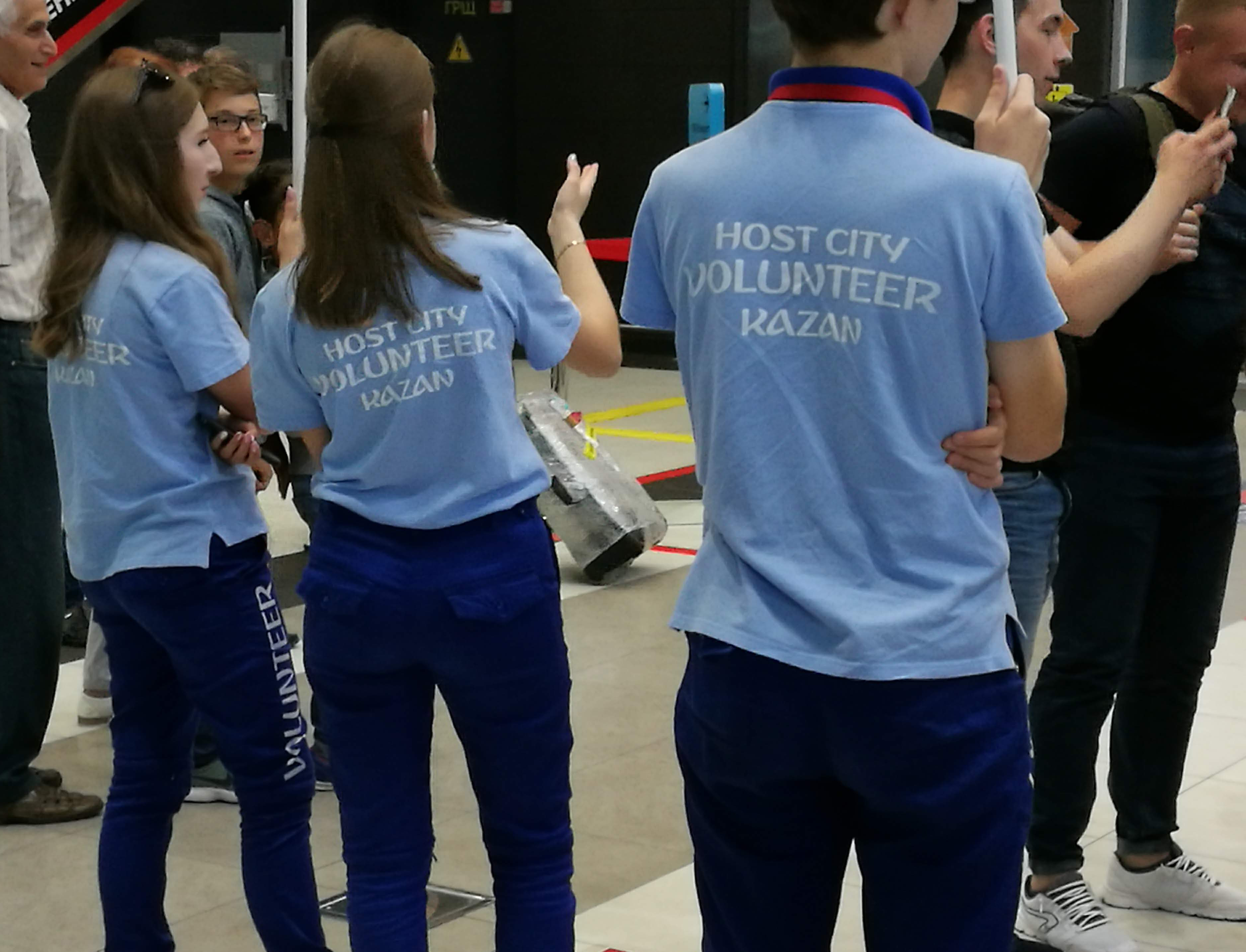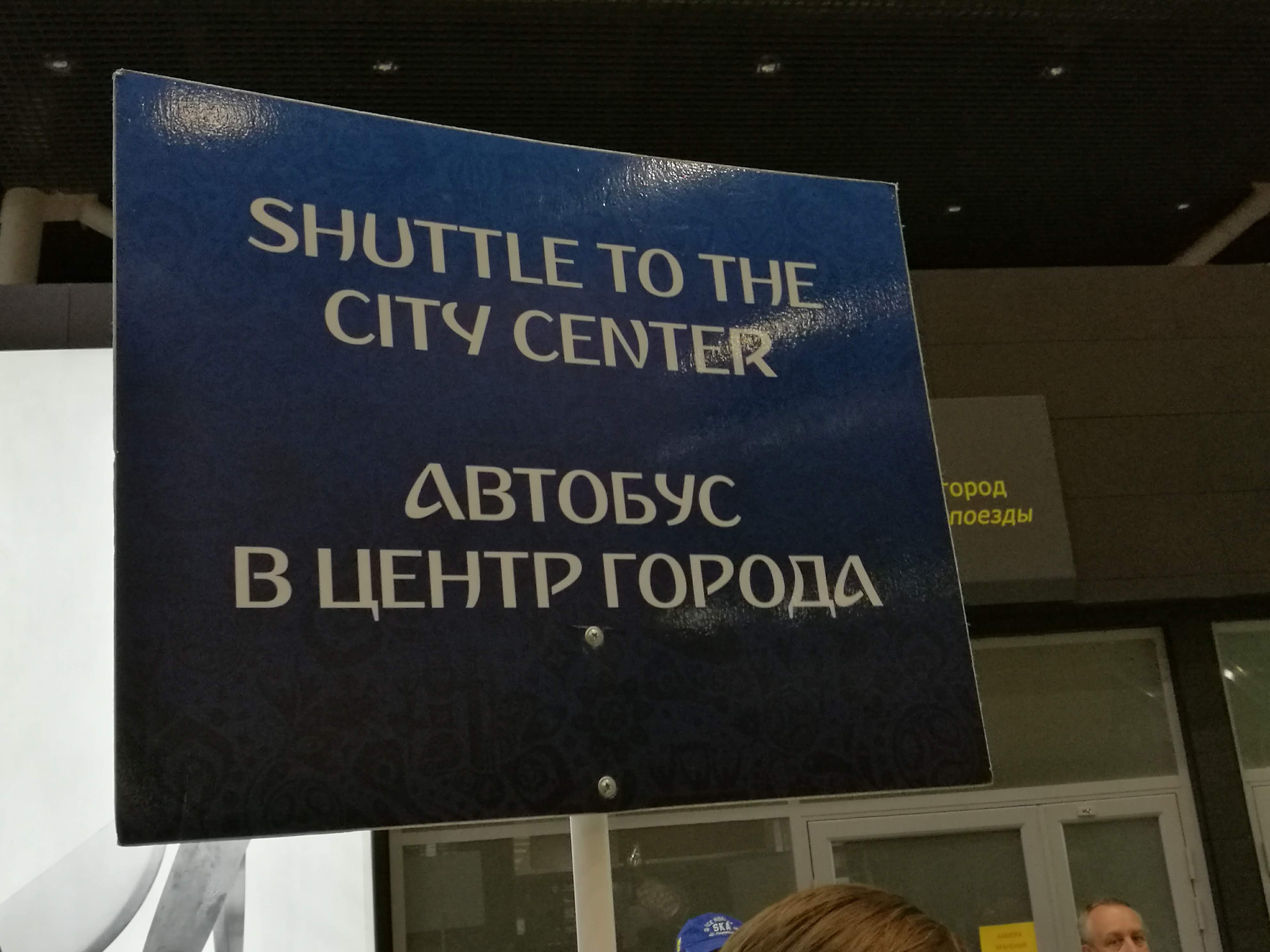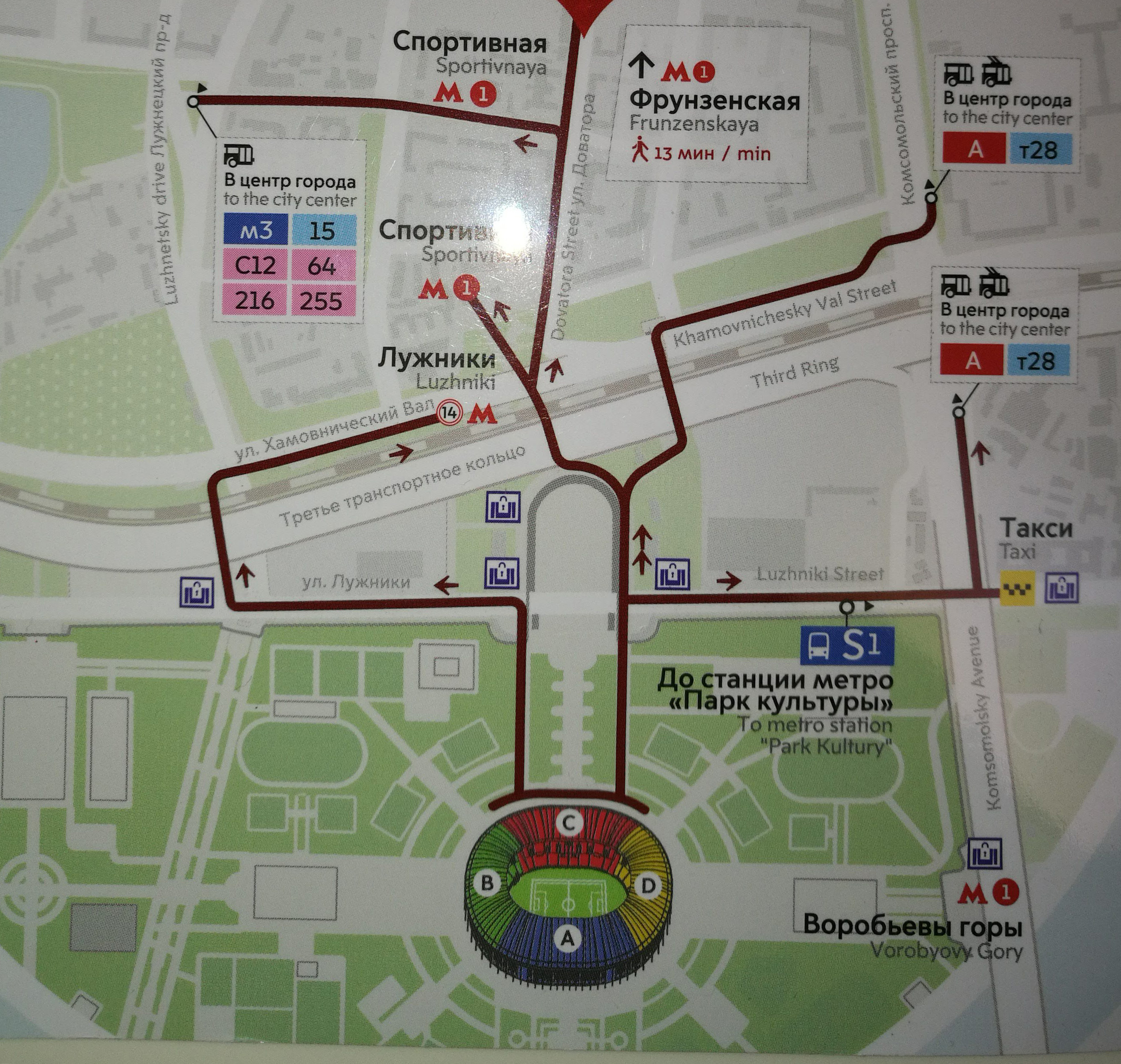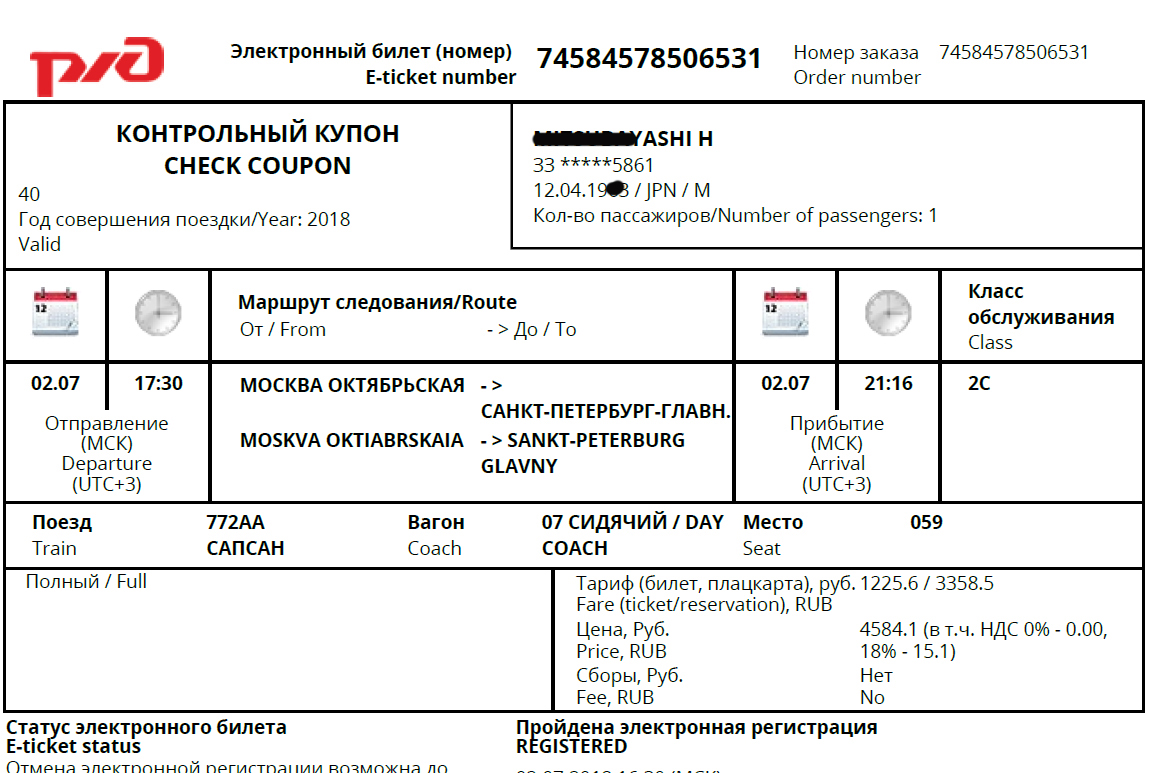海外旅行では避けては通れない時差ぼけですが、 ヨーロッパとは7~9時間の時差があり、うまく対策しないと体内時計がくるってしまいます。
せっかく楽しみにしていたヨーロッパ旅行なのに、時差ぼけのせいで体調がすぐれず観光が楽しめなければ、もったいないですよね。
体質や眠りやすさなどは人それぞれで、時差ぼけ対策はさまざまありますが、ヨーロッパ旅行歴40数回の筆者の経験から、最も良い方法と避けるべき行動をご紹介します。
☆フライトが昼か夜かによって時差ぼけ対策は異なる
ヨーロッパへ行くフライトは昼便と夜便があります。
昼便は朝10時~14時頃に出発し、ヨーロッパ到着時刻は行先や乗継の有無によって異なりますが、14時~21時頃になります。 日の光を追いかけて飛ぶことになります。
2026年1月現在、日本からヨーロッパ各都市への直行便はロシア上空を通過できないため、フライト時間は数時間長くなっています。
夜便は深夜に出発し、ヨーロッパには早朝から昼頃に到着します。
☆昼便で行く時の時差ぼけ対策
フライトの前半に寝るようにしましょう。
離陸して1~2時間後に食事が出ますので、なるべくお腹いっぱいに食べて、コーヒーなどカフェインを含む飲み物は避けて、食べ終わったら、機内が消灯されるのを待たずに、なるべくすぐに寝るのです。お酒の力を借りるのもありでしょう。
狭いエコノミー席で眠りにくい方は、たくさん食べるのがコツです。仕事中のランチで炭水化物をたくさん食べると午後、眠気におそわれる経験は多くの方がされているでしょう。午後の仕事の効率を考えて食べ過ぎないように気を使っていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうが、時差ぼけ対策では逆に眠くなるように食べるのです。
筆者は、機内食のボリュームが少なそうな時は、菓子パンなど炭水化物が多めの食糧を買って乗り込み、機内食に追加して食べて、お腹をいっぱいにしています。
たくさん食べてすぐに寝ると、睡眠が浅くなり、十分な熟睡感が得られませんが、眠れないよりは良いです。
☆夜便で行く時の時差ぼけ対策
昼便とは逆にフライトの後半で寝るようにします。
離陸してすぐに食事が出る場合と出ない場合とがありますが、出ても軽めに食べて、お酒で眠くなる方は控えて、ヨーロッパ時間で寝る時刻になるまで起きているようにします。
機内が暗くされますが、電燈をつけましょう。残業で徹夜する時と似た状況になりますが、旅行ガイドや現地の情報をネットで見るなどして、これから始まる楽しい旅に思いを馳せるといいでしょう。
現地の就寝時刻から到着前1~2時間前の食事が出されるまで眠りましょう。
眠気が続いていたら、食事を抜くのもいいでしょう。キープしておいて、着陸態勢で否応なく起きなければならなくなる直前に食べることもできます。
☆出発までの睡眠時間の調整は必要か
「現地の時間帯になるべく合わせるように、出発までに睡眠時間をずらしておく」といった時差ぼけ対策が紹介されるのをガイド本などで見かけます。睡眠時間をなるべく後ろ倒しにするということですが、筆者は無理に行わなくてもいいと思います。
フレックスタイムで仕事できる人は別として、朝の決まった時間に仕事を始める人は、ヨーロッパ旅行の前だけ、仕事を始める時間を遅くするというのは、そもそも難しいでしょう。
ただし、昼便で行く場合、余裕があればひとつお薦めがあります。フライトで眠りたい時刻に眠れるように前夜の就寝時刻を調整するということです。
午後に眠くなるのは誰でも同じですが、眠気が来る時刻は、前夜の就寝時刻から一定時間後です。平均は15時間後で、24時に就寝して7時に起きると、その日の15時くらいに眠気がくるということです。
そこで、例えば、昼便が11時発で、13時頃に食事を終えて14時に眠りにつこうとするならば、14時の15時間前である前夜23時に就寝するのがよいわけです。
15時間はあくまで平均で、ご自分の就寝から翌日眠気が来るまでの時間を把握したうえで、昼便での行きのフライト前夜に寝る時間を設定するのです。
☆到着後は寝てはならない
そして、その日の夜の寝る時刻になるまで寝てはいけません。これは昼便でも夜便でも同じで、時差ぼけ対策の鉄則です。
夜便で朝到着して、ホテルにチェックインして昼寝してしまうと、寝入った瞬間に深い眠りに入ってしまいます。30分か1時間で起きたとしても、体が眠った状態でだるくなってしまいます。そして、夜に眠れなくなります。
このサイクルにはまってしまうと数日続くこともあり、翌日から観光している午後の時間帯に猛烈な眠気に襲われることになります。典型的な時差ぼけです。
初日の昼間の眠気に耐える手段は人それぞれですが、筆者はなるべく街歩きし、眠くなったら濃いめのコーヒーを飲むようにしています。酒を飲むと眠くなるので、初日の酒は寝る1時間くらい前まで飲まないようにしています。
☆帰りのフライトでの時差ぼけ対策
ヨーロッパから帰国するフライトの時間帯は朝9時頃から23時過ぎまでさまざまありますが、日本時間で通常寝ている時間帯に機内で寝るようにします。
筆者は食事して2時間後に眠くなる傾向にあるので、眠りたい時間に合わせて、機内食を食べる時間を調整しています。
機内食は配られたらすぐに食べなければならないわけではありません。例えば、朝11時発の帰国便で13時頃に最初の機内食が出された時は、なるべく後までトレーをキープするようにします。
また、帰国便で寝る時間に合わせて旅行最終日の就寝時刻を調整しています。
24時(日本時間の就寝時刻)-8時間(時差)-15時間で最終日は1時に寝るということです。
離陸時点が日本の早朝になる夜便の時は、日本時間の夜に寝ることはできません。帰国後の時差ぼけを軽くするためには、フライトの前半に軽く寝るか、ずっと起きていることが有効です。
夜発のフライトでは、ヨーロッパ時間に慣れた体で、自然と眠りやすい状況になります。しかし、ここでぐっすり寝てしまうと、帰国した日の夜に眠れず、数日間、時差ぼけを引きずることになってしまいます。
☆時差ぼけを引きずらないための決め手
一般的に、東回りのほうが西回りより時差ぼけが起きやすいと言われています。すなわち、ヨーロッパ旅行の場合は、行く時より帰国してからのほうが時差ぼけになりやすいということです。
いったん時差ぼけになってしまうと、行った時より長引きます。そうならないためには帰国した翌日の行動が重要です。
帰りのフライトでうまく眠れたとしても、体内時計は相変わらずヨーロッパ時間になっています。ふだんの就寝時刻になっても眠れず、朝起きようとしてもつらい。
時差ぼけにならないためには、帰国当日の夜に眠れなくても、翌朝は通常の起床時間に起きて、その日は終日、昼寝厳禁にします。無理やり体内時計を日本に合わせるのです。
ヨーロッパ旅行から帰って仕事に復帰するまで1日あけて、その間に体調を整えようとされる方がいらっしゃいますが、気をつけないと逆効果になりかねません。
筆者は朝型人間ですが、帰国翌日の朝の目覚ましをかけないで寝たら、通常の起床時刻より5時間も長く昼近くまで寝てしまい、その後数日間、ひどい時差ぼけに悩まされたことがあります。
帰国翌日から即仕事の方は、なるべく手足を動かす仕事がよいでしょう。デスクワークであれば、ドキュメントを読むより、なるべく書く。できるだけ周囲の人と会話する。
☆おしまいに
さて、いかがでしたでしょうか。
ヨーロッパ旅行で時差ぼけになるかどうかは、行きと帰りのフライト中とその前後の日の過ごし方で決まります。時差ぼけ無しの快適な旅と、帰国後の生活のためには、どこかで眠気を我慢する、なんとかして寝るという無理をしなければなりません。
この記事が皆さんの快適なヨーロッパ旅行のお役に立てればうれしいです。